江戸時代の天神祭の地車図面
(H26.6.27更新)
平成16年7月14日(水)~8月30日(月)(予定)
弘化3年(1846) 山崎健治郎氏蔵
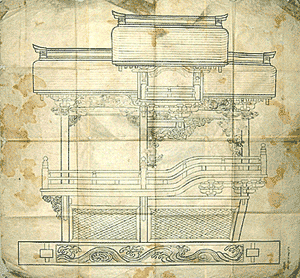
天神祭に天満市場から出された三ツ屋根地車の側面図。彫刻の図案が詳細に記されており、現存する地車と一致する部分も多くある。現存の地車の計画図面と考えられるものである。
寛政7年(1795)原図/天保3年(1832)写 山崎健治郎氏蔵
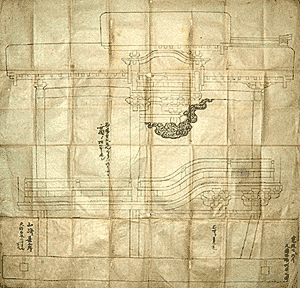
天神祭に天満市場から出された三ツ屋根地車の図面で、寛政7年に記された原図から、天保3年に筆写したもの。図中には「市場古大だんぢりハ」と書き込みがあり、この原図が書かれた寛政7年以前にも古い形式の地車が存在したことを伝える。
茨木市内の民家から新たに発見された江戸時代の天神祭の
新発見の図面は、茨木市内にお住まいの山崎健治郎さんのお宅から発見されたものです。山崎さんがご自身のルーツ研究のため、家に伝来した古文書類を本年6月に大阪天満宮に持ち込まれたことが、今回の発見につながりました。山崎家は、江戸時代から大阪天満宮近くで代々宮大工(屋号「大和屋」)を営んできた家で、地車のほか、社寺建築、町方の家の造営などを手がけてきました。
天神祭の地車は、江戸時代の最盛期には84両もの地車が宮入した記録がありますが、現在では天満市場から奉納された三ツ屋根地車を残すのみとなっています。現存の三ツ屋根地車は天満宮の記録から嘉永5年(1852)の製作とされてきましたが、今回の図面の発見により、三ツ屋根地車という形式の発生が寛政7年(1795)以前に遡ることが確認されました。
| フロア / 9階 | コーナー / まちの生活―信仰する |
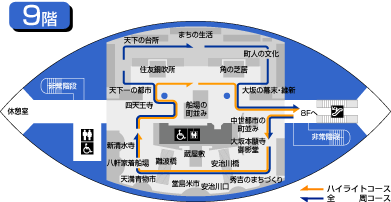 |
|