結髪雛形による髪型の再現
(H26.6.25更新)
平成17年8月24日(水)~平成18年1月16日(月)(予定)

結髪:ミナミ美容室 南 登美子氏

をとこわげ 本館蔵

めがねわげ 本館蔵
「をとこわげ」と同様、鬢や髱をつくらず、髪を天頂部に束ね上げる。髷をつくる際に、仮髪に紺紙を貼った「めがね」部分の仮髪を添える。

いたこわげ 本館蔵
「島田髷」を基本とし、髱を張り出して高めにつくり、根を取る。根のまわりには赤色鹿子を掛け回し、仮髪を蝶結びのように形作って添え、髷は勝山髷のごとく半円形に拡げる。

てまりわげ 本館蔵
髱を張り出して高めに、髷を大きくつくり、丸く膨らませるようにしながら前方へ被せて、あたかも「手鞠 」に見えるような形に結い上げる。根のまわりには銀丈長紙を添えている。

つりふねわげ 本館蔵
髱を張り出して高めにつくり、髷に笄 を置いて紺紙に貼り付けた仮髪と赤地鹿子とを掛け回す。さらに髷の上に幅広の「掛け前髪」を掛け、根元には銀元結 を長めに巻いている。

まさおかわげ 本館蔵
髱を張り出して高めにつくり、髷とする髪を中心から左右に割り、鼈甲の笄に左右から掛け回して、髷の前方へ流して結い納めた。鬢は張らず、前髪を大きくつくり、髷の根元には鹿子を括っている。『都風俗化粧伝』にいう「勝山を割りて、髪の根より笄をさし、それを前のわげの外に出して通したる結い様」とした。

りょうわ 本館蔵
髱を張り出して高めにつくり、根をとり、束のまま輪にして後ろへ廻し、先端を巻き納める。根の前に仮髪で笄を留め、仮髪を輪にして笄の下を通して添え、その上に仮髪で「橋」を掛け、橋止めをつける。根元には白丈長紙を廻し掛けた。
江戸時代後期の文化文政年間頃までに結われるようになった女性の髪型は、200種類を超えると考えられています。しかし現在でも、結いかたがわかる髪型はそれほど多くはなく、特に江戸時代の大坂の結髪文化については、現在ではほとんどわからないようになってしまいました。
そこで、このコーナーでは、文化文政年間頃の大坂でみられた女性の髪型を実際の2分の1の大きさで再現した「
この結髪雛形による髪型の再現は、文部科学省科学研究費補助金[若手研究(B)「結髪再現による化政期の髪型に関する研究」]の研究成果の一部です。
| フロア / 9階 | コーナー / まちに暮らす―装う |
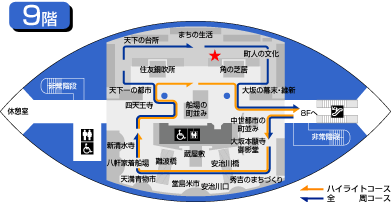 |
|