加耶土器と百済土器
(H26.6.24更新)
平成21年9月25日(金)~ 12月21日(月)(予定)

加耶土器 陶質注口土器 大阪城天守閣蔵
大阪城公園西側の大手前遊歩道で工事中に見つかりました。漫画の蛸の口のような注口が特徴です。表面には土器を叩いて作ったときの道具の痕跡(平行タタキメ)が残っています。

加耶土器

お茶碗のような形をした土器で、6世紀後半から7世紀初め頃の百済に類例がありますが、日本列島では唯一の例です。金属の椀を真似てつくられたもので、外面の線(櫛描直線文 )はその名残です。
難波は古代倭王権の対外交渉の窓口として重要な役割を果たしていました。その証拠に難波では朝鮮半島の土器が多く出土しています。今回は6世紀中ごろまで朝鮮半島南部の慶尚南道から慶尚北道南部に勢力をもっていた加耶と、日本とのつながりが深い朝鮮半島南西部の百済の土器を展示します。また、あわせて韓国で発見された土器の類例を写真展示し、難波の土器の故郷を探ります。
| フロア / 10階 | コーナー / 古代難波の序章 |
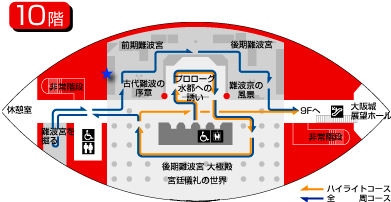 |
|