錦影絵
(H26.6.12更新)
平成23年10月26日(水)~ 11月28日(月)(予定)

錦影絵 風呂
明治時代 大阪市指定文化財 本館蔵(大森寅之進氏寄贈)
風呂は、錦影絵に用いる木製の幻灯機。ガラス板をはめこんだ種板の画像を、和紙スクリーンの裏側から投影します。演者はこれを手に持って人物を動かし、セリフも語ります。レンズの上の布はシャッターです。人物の動きだけでなく、レンズやシャッター操作などを駆使して、ズームアップ、フェードイン・アウトなど様々な映像表現が可能でした。光源は灯明、石油ランプ、電球と時代とともに変化しました。

錦影絵 種板「三番叟」
明治時代 大阪市指定文化財 本館蔵(大森寅之進氏寄贈)
種板は、幻灯のスライドにあたります。桐材にはめ込まれた薄いガラス板に、透明な絵の具と墨で人物や背景が描かれます。ガラスは二重になっていて、仕掛けの板を操作すると画像が入れ替わったり、重なったりして人物の動きなどが表現できます。
錦影絵は、幕末から大正頃まで盛んにおこなわれた幻灯機によるカラーアニメーションで、幻灯の映像を用いた芸能です。江戸時代後期にオランダから持ち込まれた幻灯機から発展したものと考えられており、日本のアニメーションの源流といわれることもあります。大阪では御霊神社境内に常設の小屋ができるほど人気があり、江戸周辺では「写し絵」、中国地方では「影人形」、「影絵でこ」などとよばれ、広い地域で楽しまれていましたが、大正時代以降は映画の隆盛に押されて衰退しました。
当館所蔵の種板は、大阪で活躍した錦影絵師、富士川都正が用いていたもので、一時は喜劇の曾我廼家五郎(1877~1948)が所蔵していました。落語ネタやチャンバラ活劇など約40演目820枚が残されており、錦影絵関係資料では最大級のコレクションです。今年4月に大阪市指定文化財となりました。今回は、その一部をご覧いただきます。(澤井浩一)
平成23年11月20日には大阪市教育委員会(文化財保護課)と共催の錦影絵のイベントも予定しています。詳しくは教育委員会ホームページで。
| フロア / 7階 | コーナー / 上方芸能の展開 |
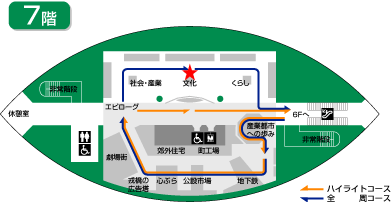 |
|