前期難波宮以前の瓦
(H26.6.12更新)
平成24年2月15日(水)~ 5月14日(月)(予定)

蓮の花を彫った木の型(笵)に粘土を押し込めて作った、屋根の軒を飾る瓦である。細部の特徴から四天王寺創建瓦と同笵であり、前期難波宮よりも古いことがわかっている。写真の瓦は上町台地北端(博物館近隣)や天王寺区細工谷遺跡で出土した。

小型鴟尾と小型丸瓦
小型鴟尾(写真左)は羽根形の文様を4段以上削り出していて、高さが17cm程度であったと推定される。また、小型丸瓦は2点あり、うち右側のものの長さは4cm程度である。いずれも通常の鴟尾や丸瓦の1/8~1/10程度であることから、法隆寺の玉虫厨子(たまむしのずし) のような小建築に用いられたのであろう。前期難波宮と仏教のつながりを示すものとして注目できる。
難波宮やその周辺の発掘調査では、しばしば前期難波宮よりも古い瓦が発見されます。その中のいくつかは四天王寺が創建されたときに使用された蓮華文軒丸瓦と同じ型を使っていて(同笵瓦)、その特徴から、枚方市・八幡市の樟葉平野山瓦窯で生産された可能性が高いと考えています。
これらの瓦は仏教に関する建物に葺かれたのでしょうか、それとも「外交の窓口難波」に見合う外交関連の建物に葺かれたのでしょうか。興味は尽きません。
今回、このような難波宮以前の瓦の中で、四天王寺創建時の蓮華文軒丸瓦と同笵の瓦について、常設展示ですでに陳列されている2点に加え、7点新たに展示します。前史を考える上でも重要な資料をこの機会にぜひご覧ください。
また、同時に前期難波宮の時期に、厨子のような小建築に用いられたと思われる小型鴟尾と小型丸瓦も展示しますので、あわせてご覧ください。
(寺井誠)
| フロア / 10階 | コーナー / 特設展示コーナー |
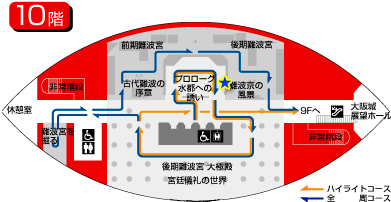 |
|