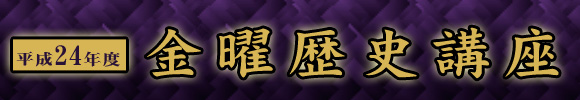
金曜歴史講座とは、(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所とともに行う普及啓発事業として、大阪の歴史や文化財の最新情報をお届けする連続講座です。
第1シーズン
| 第126回 6月27日(金) | 市川 創 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 見えてきた大坂城 ―山里丸の発掘調査から― | |
| 山里丸は大坂城本丸の北部に位置し、天守台よりも1段低くなった曲輪くるわです。 2011年度の調査では、豊臣期の金箔瓦が出土したほか、徳川期の大規模な集水枡が見つかりました。 また、地下のようすを探るために行った電気探査でも興味深い結果が得られています。 こうした考古学的な成果から、大坂城の姿を描いてみたいと思います。 | |
| 第127回 7月 6日(金) | 趙 哲済 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 長柄砂州の成りたち | |
| 上町台地の西側には長柄砂州と呼ばれる砂州があります。 この砂州は弥生時代にできましたが、中央区北浜~本町付近では、大川の流れに伴って大きくなりました。 一方、南の浪速区日本橋~今宮付近では、砂州と台地の間に砂泥干潟ができ、やがて古墳時代末~古代には砂浜になりました。 今回は、このような砂州の成りたちに注目してみます。 | |
| 第128回 7月13日(金) | 高橋 工 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 見えてきた孝謙天皇の「東南新宮」 ―難波宮宮殿東方の発掘調査― | |
| 近年、難波宮の発掘調査では宮殿周辺部で目覚ましい成果が上がっています。 ここ3年間に宮殿東方で見つかった遺構と、約50年前、山根徳太郎博士による難波宮発見の頃の発掘成果を合わせて検討すると、 文献にみえる孝謙天皇の「東南新宮」がおぼろに浮かび上がってきました。 | |
| 第129回 7月20日(金) | 長山 雅一 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 山根徳太郎先生と難波宮 | |
| 7月28日は、難波宮の発見者・故山根徳太郎博士の命日です。偶然だと思いますが、7月28日は「なにわ」と読めます。昨年は難波宮跡の大極殿の発見から50年でした。今年は次の50年に向かう年になります。今では山根先生を直接知る人は少なくなりました。そこで、難波宮跡の発見への道のりと先生のご苦労などを振返ってみたいと思います。 | |
| ※演題・内容等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 | |
| 開催場所 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
| 時 間 | 午後6時30分~7時45分 |
| 定 員 | 250名 |
| 申込方法 | 当日先着順 ※午後6時より受付開始 |
| 参加資料代 | 各回 200円 |
| 問い合わせ | (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所「金曜歴史講座」係 電話:06-6943-6833 http://www.occpa.or.jp 大阪歴史博物館「金曜歴史講座」係 電話:06-6946-5728(代表) ※火曜日は休館です |