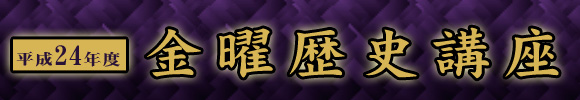
金曜歴史講座とは、(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所とともに行う普及啓発事業として、大阪の歴史や文化財の最新情報をお届けする連続講座です。
第2シーズン
| 第130回 9月21日(金) | 谷﨑 仁美 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 阿倍寺が幻でなくなる日 ~最近の発掘調査成果~ | |
| 阿倍寺跡は、近鉄阿部野橋駅の南側に所在する白鳳寺院で、有力氏族の阿倍氏の寺だと言われています。昨年末から中心部での発掘調査がいくつか行われました。今回、その最新成果を紹介しつつ、 歴史の表舞台で活躍した阿倍氏の寺を再評価してみたいと思います。 | |
| 第131回 9月28日(金) | 黒田 慶一 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 見えてきた法安寺 ―難波宮跡と重複する寺院跡― | |
| 難波宮史跡公園のある“中央区法円坂”という町名は、幕末まで存在した“法眼坂”(ほうげんさか)という坂道に由来し、“法眼”は難波宮跡の北側に存在した延喜式内社の「難波坐生国咲国魂神社」の神宮寺だった「法安寺」からの転訛と言われます。去年春に森ノ宮中央2丁目で発見された、中世の「お堂」跡から法安寺に迫ります。 | |
| 第132回 10月5日(金) | 伊藤 幸司 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 弥生時代の鋳造技術 ―鞴(ふいご)を使用せず青銅を熔かす「自然吹」の検証― | |
| 弥生時代、銅鐸や銅剣、銅鉾など多くの青銅製品が製作されました。我が国における金属器生産の黎明期といってもよいでしょう。これらの青銅製品のほとんどは鋳造でつくられ、その製作工程では金属を溶解するための設備・技術が必要でした。今回は弥生時代の一時期に出現して消えた「曲がり羽口」に注目し、その使用方法の復元実験からわかってきた当時の金属溶解技術についてお話しいたします。 | |
| 第133回 10月12日(金) | 松本 百合子(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 高松藩蔵屋敷跡の調査 ―「天下の台所」を掘る― | |
| 江戸時代の中之島周辺は各藩の蔵屋敷が置かれ、 国元の年貢米や特産物が集まる経済の中心地として繁栄しました。 高松藩蔵屋敷はなかでも立地が良く、面積的にも有数の規模を誇っていました。 調査でわかった蔵屋敷内のようすをご紹介します。 | |
| ※演題・内容等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 | |
| 開催場所 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
| 時 間 | 午後6時30分~7時45分 |
| 定 員 | 250名 |
| 申込方法 | 当日先着順 ※午後6時より受付開始 |
| 参加資料代 | 各回 200円 |
| 問い合わせ | (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所「金曜歴史講座」係 電話:06-6943-6833 http://www.occpa.or.jp 大阪歴史博物館「金曜歴史講座」係 電話:06-6946-5728(代表) ※火曜日は休館です |