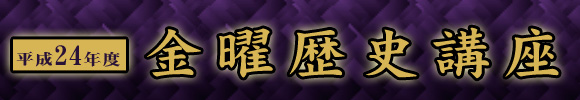
金曜歴史講座とは、(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所とともに行う普及啓発事業として、大阪の歴史や文化財の最新情報をお届けする連続講座です。
第3シーズン
| 第134回 11月30日(金) | 松本 啓子 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 鎖国期日本に輸入されたヨーロッパ陶器 | |
| 鎖国期のヨーロッパ・マジョリカ陶器の大坂出土品から、ヨーロッパと日本の社会的背景を探ります。 この陶器は17世紀に日本の上流層に流通した壺です。カトリックを嫌った鎖国期に、 プロテスタントのオランダ連合東インド会社から調達したものとみられますが、 当時のヨーロッパでは、マジョリカ陶器はカトリックと強く結びついています。 出土例・伝世例などから、マジョリカ陶器の流通と日本招来の背景を考察します。 | |
| 第135回 12月7日(金) | 櫻田 小百合 (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 竪穴建物からみた弥生時代 ―弥生時代の始まりと古墳時代への胎動― | |
| 弥生時代の竪穴建物の形には地域や時期によって差異がみられます。 各地域の竪穴建物の形のちがいや、それぞれの時期ごとの変化をみることで、 人々の交流や社会の変化の様子を垣間見ることができます。 今回は、縄文時代から弥生時代、弥生時代から古墳時代への過渡期にスポットをあて、 その時の人々が生活していた竪穴建物の形からどんなことがわかるのか、 竪穴建物の復元実験からわかったこともふまえてお話したいと思います。 | |
| 第136回 12月14日(金) | 田中 裕子(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 中国における鉄利用の始まり ―科学分析が語る中国古代の鉄製品― | |
| 私たちの生活にとって身近な金属である鉄は、 いつ、どのような姿で出現し、用いられるようになったのでしょうか? 古代東アジアの中心である中国では、 紀元前5世紀を溯る多くの鉄製品が発掘調査でみつかっており、 金属学的な分析によって材質や製作技術についての研究が進められています。 本発表では、中国出土の初期の鉄製品について、 科学分析の成果に基づき、 その材質や技術の変遷と導入経路についてご紹介いたします。 | |
| 第133回 12月21日(金) | 清水 和明(公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所 |
| 近世大坂の骨細工業 ―双六コマの作り方からわかること― | |
| 近世大坂の発掘調査では、骨細工製品だけでなく途中の加工品も見つかることから、 都市に職人が住み細工業を営んだことがわかっています。ただ資料は腐りやすく、 作業を検証する材料はこれまでわずかでしたが、 昨年度の城下町跡の発掘資料から、双六コマの製作工程を詳細に復元することができました。 そこから骨細工業と職人の関係やその技術について考えてみます。 | |
| ※演題・内容等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 | |
| 開催場所 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
| 時 間 | 午後6時30分~7時45分 |
| 定 員 | 250名 |
| 申込方法 | 当日先着順 ※午後6時より受付開始 |
| 参加資料代 | 各回 200円 |
| 問い合わせ | (公財)大阪市博物館協会 大阪文化財研究所「金曜歴史講座」係 電話:06-6943-6833 http://www.occpa.or.jp 大阪歴史博物館「金曜歴史講座」係 電話:06-6946-5728(代表) ※火曜日は休館です |