難波宮で見つかった建築金物
(H25.5.28更新)
平成25年5月29日(水)~8月26日(月)予定
難波宮の発掘調査では、柱や基壇の痕跡から当時の建物の大きさや配置などを知ることができます。しかし、その上に建つ建物がどのような姿をしていたのかは、容易には分かりません。そこで重要となるのが発掘調査で見つかる建築部材です。
ここでは前期・後期難波宮、それぞれの調査で見つかった部材のうち、建築金物について紹介します。 (李陽浩)
鉄釘
(左:西八角殿から出土、右:前期難波宮東方の谷から出土)
前期難波宮東方の谷の調査で見つかりました。西八角殿の調査でも見つかっており、前期難波宮に釘が使われたことを示す例として貴重です。釘の用途は不明ですが、大きさや形を唐招提寺の例と比較すると、垂木止めに使われた可能性があります。
饅頭金物
(内裏西方官衙の谷から出土)
門扉(もんぴ)の釘隠(くぎかく)しに用いられる飾り金具で、唄(ばい)ともいいます。当館敷地内の発掘調査で見つかりました。古代の例では、法隆寺綱封蔵や唐招提寺金堂(木製)などが有名です。後期難波宮にも寺院建築と同じような金具が使われたことがわかります。
| フロア / 10階 | コーナー /特設コーナー |
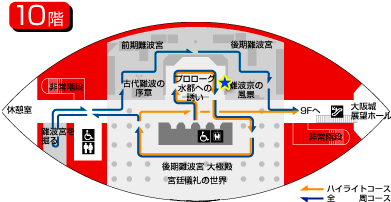 |
|