前期難波宮水利施設出土の祭祀遺物
(H26.9.23更新)
9月25日(木)~
7世紀半ばにつくられた前期難波宮の北西部(当館のすぐ西側)では、谷を利用し、湧き水を利用する施設と大規模な石組溝からなる水利施設が見つかっています。この施設から人形(ひとがた)、斎串(いぐし)、土馬(どば)などの祭祀遺物が見つかりました。このような祭祀遺物を組み合わせて行う祭祀は、古代の基本法典である律令(りつりょう)にも記されていることから、7世紀末の藤原京以降に現れると考えられていたのですが、7世紀半ばの前期難波宮の段階で、すでに行われていたことが明らかとなりました。人形は身についたケガレをうつし、水に流す祓(はら)いに使われ、斎串は周囲に突き立てて結界をつくるのに用いられたと考えられています。今回展示する祭祀遺物は泉で見つかっていることから、祓いの他に貴重な水源に対する祭祀にも用いられた可能性もあります。
古代の人々の内面にふれることのできる資料をこの機会にご覧ください。
(村元健一)
| フロア / 10階 | コーナー / 前期難波宮の姿を求めてコーナー |
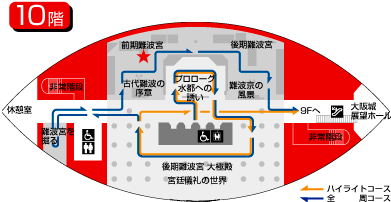 |
|
