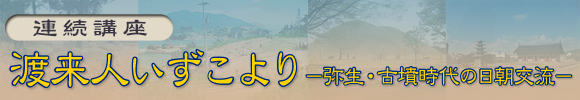
大阪歴史博物館では、平成28年2月22日、29日、3月7日、14日(いずれも月曜日)に連続講座「渡来人いずこより-弥生・古墳時代の日朝交流-」を開催します。
今回は、弥生~古墳時代に朝鮮半島から日本列島にやってきた「渡来人」にスポットを当てます。この時期の渡来人は、さまざまな新文化を携えてきて、弥生・古墳文化を大きく発展させる要因にもなりました。その渡来人が朝鮮半島のどの地域からやってきたのか、また、どんな文化を携えてやってきたのかという、具体的な姿に踏みこんで話をします。講座を通じて、日本文化に加え、朝鮮半島の歴史・文化に対する理解を深め、隣国に対してさらに親しみをもつきっかけになれば幸いに思います。
この機会にぜひご参加ください。
講座の内容
第1回:2月22日(月) 講師:寺井誠
「輝きとの出会い-金属器生産と渡来人-」
 ■野幕支石墓群(全羅南道高興郡)
■野幕支石墓群(全羅南道高興郡)
金属器の登場は、それまでその輝きを見たことがなかった倭人にとって、おそらく衝撃的なものであったでしょう。紀元前4~5世紀ごろから北部九州を中心に各地で銅剣・銅矛などの金属器生産が、朝鮮半島からの渡来人が関わりながら始まったことが確認されています。第1回の講座では、有明海沿岸などで見られる渡来人集落と金属器生産の関係について紹介しながら、北部九州における弥生時代の展開について話をします。
第2回:2月29日(月) 講師:寺井誠
「楽浪郡の興亡と対外交渉の変化」
 ■紀元前後の交易拠点 勒島遺跡の発掘調査風景(慶尚南道泗川市)
■紀元前後の交易拠点 勒島遺跡の発掘調査風景(慶尚南道泗川市)
紀元前108年、超大国である漢王朝が、朝鮮半島北部に楽浪郡を設置します。これにより、韓(朝鮮半島南部)と倭(日本列島)に高度な中国文明が流れ込む契機となり、国家形成に向けての大きな第一歩を踏み出します。また、楽浪設置によって半島と列島の交流が活発になることが考古資料で明らかになっています。第2回の講座では楽浪郡が存続する4世紀までの倭の対半島交渉について話します。
第3回:3月7日(月) 講師:寺井誠
「渡来文化に見える新羅」
 ■新羅王墓 皇南大塚(慶尚北道慶州市)
■新羅王墓 皇南大塚(慶尚北道慶州市)新羅は朝鮮半島南東部に勢力を持ち、やがては朝鮮半島を統一する国です。『日本書紀』をひも解くと、たびたび新羅との対立記事が目につきます。はたして、新羅は倭と仲が悪く、没交渉だったのでしょうか?でも、各地で新羅系の資料が発見されているのは事実です。第3回の講座では、新羅の歴史や主要な遺跡、日本列島出土の新羅系資料などを紹介しながら、新羅は倭にどのようにかかわったのか話します。
第4回:3月14日(月) 講師:寺井誠
「渡来文化に見える百済」
 ■百済寺院 定林寺址(忠清南道扶餘郡)
■百済寺院 定林寺址(忠清南道扶餘郡)
百済は朝鮮半島南西部にあった国です。『日本書紀』には、百済から仏教が伝えられたり、五経博士が派遣されたりした記事があり、友好国であったように見えます。近畿地方でも、百済人が馬の飼育や、最新技術の伝来に関わっていたことが分かる遺跡がいくつかあります。第4回の講座では、百済の歴史や主要な遺跡、日本列島出土の百済系資料を紹介しながら、文献史や考古資料を基にして、百済と倭が接近する背景について考えてみたいと思います。
| 連続講座 渡来人いずこより-弥生・古墳時代の日朝交流- | |
|---|---|
| 日 時 | 平成28年2月22日、29日、3月7日、14日 いずれも月曜日、午後2時~4時 |
| 会 場 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
| 講 師 | 当館学芸員 寺井誠 |
| 参 加 費 | 2,000円 (4回通し、初回受納) ※参加されない回があっても返金できませんので、あらかじめご了承ください。 |
| 定 員 | 250名(事前申込制、応募者多数の場合は抽選) |
| 応募条件 | 4回通しで参加できる方 |
| 申込方法 | 往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号、返信用はがきの宛先を必ず書いて、お申し込みください(はがき1枚につき1名の申し込みに限ります)。
※全4回一括での申し込みとなります。特定の日のみの申し込みはできません。 |
| 問い合わせ | 大阪歴史博物館 「連続講座 渡来人」係 (電話)06-6946-5728 (ファクシミリ)06-6946-2662 |