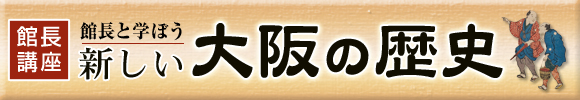
(H29.1.27更新)
当館学芸員が研究する大阪にかかわる歴史や美術を、栄原館長とともに学ぶ講座です。
講座では、まず講師が講演を行い、その後、館長と講師による質疑応答を行います。
| 第13回 平成29年 2月10日(金) | 講師:八木 滋 |
「江戸時代初期の大坂の「町(ちょう)」」 江戸時代の都市の基礎単位であった「町(ちょう)」。しかし、江戸時代初期(17世紀前半)の町についてはあまりよくわかっていません。今回は、大坂の都市開発の過程を踏まえながら、数少ない町の史料を読み込み、その実態に迫ります。 |
|
| 第14回 平成29年 2月17日(金) | 講師:村元 健一 |
「複都制と古代難波」 複数の都を置く「複都制」は飛鳥・奈良時代の都城研究の重要なテーマです。難波はこの時代に都が置かれており、複都制を考える上で欠かすことはできません。今回は近年の研究の盛り上がりを受けて、難波と複都制について考えます。 |
|
| 第15回 平成29年 2月 24日(金) | 講師:松本 百合子 |
「なにわの油火(あぶらひ)」 現代人にとってはあたりまえでも古代人には貴重な明かり。難波の人々はどのようにして明かりを得ていたのでしょうか。また、明かりはどのような場面で用いられたのでしょうか。大阪から出土する古代の灯火具からひもときます。 |
|
| 第16回 平成29年 3月 3日(金) | 講師:岩佐 伸一 |
「大坂の狩野派絵画-江戸時代を中心に-」 狩野元信や永徳、探幽らの名手を輩出した狩野派は、室町時代以降、代々の権力者に愛好されました。江戸時代の中期になると、主に町人を顧客とした狩野派の絵師が大坂で活躍をしました。今回は大坂の狩野派と画家の紹介をします。 |
|
| 館長講座「館長と学ぼう 新しい大阪の歴史」 | |
|---|---|
| 会 場 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 交通のご案内 |
| 時 間 | 午後2時00分~3時30分(開場は午後1時30分) |
| 定 員 | 各回250名(当日先着順) |
| 参加方法 | 直接会場へお越しください。 |
| 参 加 費 | 各回200円 ※「キャンパスメンバーズ」会員校(大阪市立大学、大阪大学、大阪府教育センター附属高等学校、大阪教育大学)の方は、証明証提示により本講座に無料で参加できます。 |