なにわの油火 ―古代~近世の灯明皿―
(H29.2.24更新)
平成29年2月22日(水)~4月(予定)
古代の灯明は、仏教儀式や貴族の住宅で使う特別な明かりでした。近世に菜種油が量産され庶民に灯明が普及するまで、灯明皿は使用者が限定され、出土地も限られる特別なうつわでした。今回は、難波宮の時代から近世の大坂城下町の時代まで、29点の灯明皿を集めました。時代ごとの灯明皿の変遷をご覧ください。
(松本百合子)

須恵器 杯
細工谷遺跡 奈良時代中頃(8世紀中葉) 直径9.2㎝
一般的な杯より口縁が強く外反し端部が横に広がるため、灯明専用の器と考えられます。口縁内面には、幅約1㎝の灯心痕がふたつ並んで残っています。細工谷遺跡は難波宮の南約2kmに位置し、付近に「百済尼寺」など、寺院の存在が指摘されています。

土師器 杯
細工谷遺跡 奈良時代中頃(8世紀中葉) 直径11.8㎝
口縁内面に2か所、幅約1㎝の灯芯痕が残ります。古代の灯明皿に残る灯心痕の多くは幅約1㎝で、布製の灯心を使っていたと考えられています。奈良時代の記録である正倉院文書には、「望陀布」と呼ばれる麻布を灯心に用いていた記録があります。
| フロア / 10階 | コーナー / 難波京の風景 |
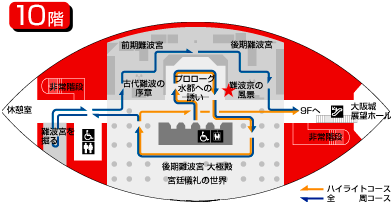 |
|