古代の刀子 と大刀
(H29.7.19更新)
平成29年7月19日(水)~ 9月11日(月)(予定)
1,600年前(古墳時代中期)の日本では、鉄の道具が普及しました。ここに展示している鉄製の刀子はそれ以降、広く用いられるようになった小刀で、腰帯に差したり、そこから垂らして身につけていました。刀子の中には鞘(さや)からすぐ抜き出すことができるように、柄(つか)が湾曲したものもありました。一方、大刀は長いために、腰につけた状態で鞘から抜くことは難しく、鞘ごと外したのち抜刀していました。平安時代後期に成立する「日本刀」と違って、この時代の刀子や刀は反りが無いといった特徴もご覧ください。
(杉本厚典)

刀子と錫 装の柄
大阪市平野区喜連東(きれひがし)遺跡 古墳時代中期(5世紀後半)大阪文化財研究所保管 全長16.0㎝
刀身の基部に鑢座(やすりざ)を持った「刀子造」の資料です。柄元(つかもと)の縁金物は幅1.7㎝の鉄板で、柄元部分を帯状に削ってはめ込んでいます。柄頭(つかがしら)は錫製の2枚の薄板を合わせて装飾しています。合せ目を隠すために、目に沿って錫線を置き、それを細かな鉄釘で固定しています。また錫線の上には刻み目、柄頭中央に列点文を入れて装飾しています。
| フロア / 10階 | コーナー / 特設展示コーナー |
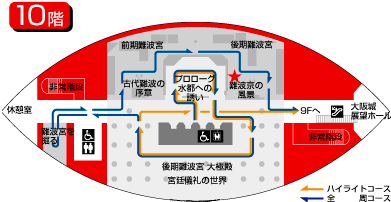 |
|