港の賑わい―木津川口と松前・江差―
(H29.7.27更新)
平成29年7月19日(水)~ 8月28日(月)(予定)
大阪は、古代の難波津以来、港として発展してきました。今年は、大阪が「開港」すなわち海外に門戸を開いてから150年目の区切りの年にあたります。このコーナーでは、江戸時代の大坂の港の賑わいを描いた「川口遊里図屏風」と、大坂に産物をもたらした松前・江差の様子を描いた「松前江差屏風」を展示します。8階の特集展示「大阪町めぐり 安治川と天保山」と合わせてご覧ください。
(八木・伊藤)
川口遊里図屏風と松前江差屏風

川口遊里図屏風
17世紀前半 10曲1隻 本館蔵 大阪市指定有形文化財17世紀前半の上方で、大きな川の河口にある遊里の様子を描いていた屏風。位置関係などから、描かれているのは、大坂木津川口の三軒家(大阪市大正区)にあった遊里ではないか推定されている。遊里の賑わいだけでなく、川を行き来するさまざまな船なども詳しく描写されている。
松前江差屏風
龍圓斎小玉貞良筆 18世紀中頃 6曲1双 個人蔵江戸時代、アイヌの人たちとの交易で財を成した近江商人が、アイヌ絵を得意とする松前在住の絵師に描かせた屏風。ニシン漁で活気づく江差の春と、城下町・松前の秋のようすが描かれている。北海道と大阪を1年に1往復した北前船は、松前・江差からニシンや昆布などの産物を大阪に運んだ。
| フロア / 9階 | コーナー /まちの生活コーナー |
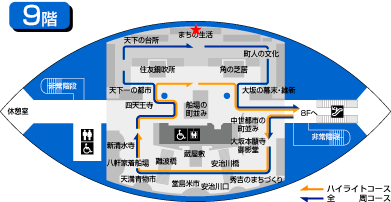 |
|