魚をとる 弥生・古墳時代の大阪の漁法
(H29.12.21更新)
平成29年12月14日(水)~ 平成30年3月5日(月)(予定)
弥生時代以降、大阪湾や淡水化が進んだ河内湖周辺では、水辺の環境や対象のえものにあわせてさまざまな漁が行われてきました。
古墳時代中期以降になると、河内湖沿岸や河川周辺では刺網・投網などの小型の網漁が、大阪湾沿岸ではこれに加えて曳網漁や飯蛸漁が行われていたようです。出土する漁具には網につけるおもり「土錘(どすい)」やたこつぼ漁に使用する「飯蛸壺(いいだこつぼ)」などがありますが、これらの形や大きさの違いがはっきりと現れるようになります。
ここでは、大阪市内の遺跡から出土する弥生~古墳時代の漁具を展示し、現代の漁業にも通じる1400年以上も前の漁の風景を見つめます。
(安岡)

展示風景
| フロア / 10階 | コーナー / 難波京の風景 |
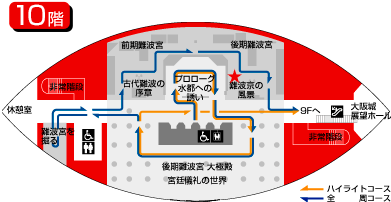 |
|