長原遺跡から出土した弥生時代中期の鋳造関連遺物
(2019.5.8更新)
2019年5月8日(水)~
弥生時代(2,800~1,800年前)は銅鐸(どうたく)・銅戈(どうか)、銅鏃(どうぞく)などの青銅製の祭器、武器が用いられた時代です。しかし青銅器を製造していたことを示す証拠は極めて少なく、大阪市内では今回紹介する長原遺跡の2002・2003年度調査(長吉長原東一丁目)の出土品のみです。
この調査では、とかした金属を鋳型に注ぎ込むための取瓶(とりべ)とみられる容器(トリベ形土器)や、高温をおこすために炉に空気を吹き込む送風管などが出土しています。トリベ形土器は、「高杯状土製品」と呼ばれているタイプで、脚部が太く、器壁が分厚くて頑丈なつくりです。炉跡やスラグは見つかっていませんが、長原遺跡でも青銅器を製作していた可能性が高いといえます。
(杉本)
| フロア / 10階 | コーナー /特設展示 |
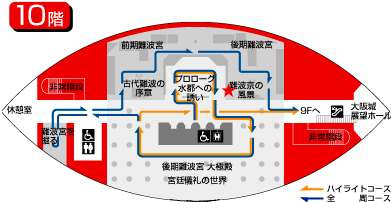 |
|
