豊臣期のすり鉢
(2022.3.15更新)
2022年3月9日(水)~ 4月25日(月)
豊臣期といえば、絢爛豪華な桃山文化が花開いた時代です。今回紹介するのは、一見するとそんな時代にはふさわしくないような、庶民の生活の道具です。
すり鉢は、中世・近世の遺跡で普遍的に出土する生活必需品の1つです。豊臣期に最も多く出土する備前焼を筆頭に、丹波焼・信楽焼・唐津焼の合計4種類を展示しました。口の部分の形状やすり目、土の質などに産地ごとの特徴が表れています。
人々はいったい何をすり鉢ですりつぶしていたのでしょうか。そのことを知るための手掛かりは少ないです。いっぽう、多くのすり鉢が発掘調査で出土する状況を踏まえると、すり鉢ですりつぶす行為が暮らしの中で欠かせない調理の方法として定着していたことが想像できます。
すり鉢には美術品のような華やかさはなく、質素で無骨な印象を受けます。しかし、無骨さの中になんとなく愛着が持てるような気がします。豊臣期の大坂に暮らした人々の“生活感”をご堪能ください。
(岡本 健)
| フロア / 9階 | コーナー /天下一の都市 |
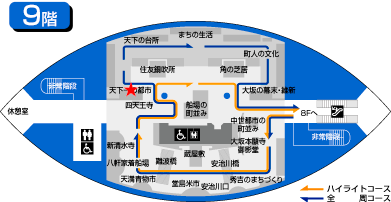 |
|
