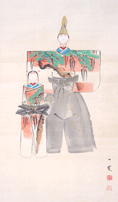|
|
|
(1)次郎左衛門(じろうざえもん)雛 江戸時代/大阪歴史博物館蔵 |
|
|
|
 |
京都の雛人形師・雛屋(ひなや)次郎左衛門が江戸時代中期に創始した雛人形で、丸い顔に引目鉤鼻(ひきめかぎばな)という面相です。次郎左衛門は宝暦(ほうれき)年間(1751~64)に江戸・日本橋室町に店を出したため、江戸の雛人形としても大変普及しました。
|
|
|
|
(2)古今(こきん)雛 江戸時代/個人蔵 |
|
|
|
古今雛は、有職雛(ゆうそくびな)(※)をもとにして、明和(めいわ)年間(1764~1771)に、江戸日本橋十軒店の原 舟月(しゅうげつ)が創案したといいます。派手な衣裳が特徴で、有職の世界にとらわれず、庶民のあこがれの雛人形を目指して製作され、明治以降の雛は基本的にこの形式を踏襲しています。
-
|
|
 |
|
|
| ※ 有職雛とは、有職故実(ゆうそくこじつ)という公家社会のしきたりにのっとって装束を正しく考証して作られた雛人形のこと。主に、京の公家社会を中心に飾られました。男雛は束帯(そくたい)姿、女雛はおすべらかしに裳唐衣姿(もからころも:いわゆる女房装束。唐衣に裳をつけた女房の日常服。)で宝冠はつけないなどの特徴を持っています。 |
|
|
|
(3)立雛図(たちびなず) 江戸時代/大阪歴史博物館蔵
森 一鳳(いっぽう)画 |
|
|
|
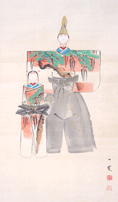 |
紙製の立雛を描いた立雛図は、女児の成長を祝う三月三日の桃の節句にかけられ、季節の画題として数多く描かれました。雄雛、雌雛の衣には、ともに松に藤図を繊細な筆線で描き、招福の意をこめています。 |
|
|
|
森 一鳳(もり・いっぽう)
寛政10年~明治4年(1798~1871)
播州吉田の生まれで、森 徹山に学び、その息女・柳の婿養子となった人物です。一鳳の描く「藻刈図(もかりず)」は、“藻刈(もかる)一鳳(いっぽう)”=“儲(もう)かる一方(いっぽう)”という語呂合(ごろあ)わせで、大変にもてはやされたといいます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|