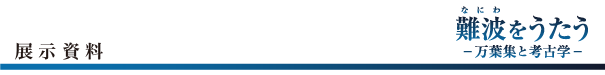
「はるくさ」木簡 (万葉仮名文木簡)
大阪市指定文化財
飛鳥時代(7世紀中頃)難波宮跡(大阪市中央区)
大阪市教育委員会蔵・大阪市文化財協会保管

【期間中展示替えあり。 レプリカ(10/2~11/8)、実物(11/10~12/5)をそれぞれ展示】
(左から:出土品、赤外線写真、実測図、本文)重圏文鬼瓦
奈良時代(8世紀)難波宮跡(大阪市中央区)
大阪市教育委員会蔵・大阪市文化財協会保管

飛鳥時代の難波宮(前期難波宮)が焼亡後、奈良時代、聖武天皇の時代に難波宮は再建されました(後期難波宮)。この宮殿の棟を飾る鬼瓦は、縁と中央に3条の凸線を入れた幾何学的な文様で、重圏文鬼瓦と呼ばれます。一部のものには中央に方形の孔があり、この孔に釘を打って棟端に取り付けられました。斬新なデザインの重圏文鬼瓦は「今は都引き都びにけり」と称えられた難波宮を象徴する瓦の一つです。
古代の漁具
飛鳥~奈良時代(7~8世紀)遠里小野遺跡
(大阪市住吉区)
大阪市教育委員会蔵・大阪市文化財協会保管

かつて大阪湾に面していた浜辺の遺跡では、土錘・イイダコ壺等の漁具がよく出土します。土錘とはおもりのことで、管状と棒状のものがありました。25~30gの棒状土錘は小型の刺網漁用で、クロダイ、スズキ、ヒラメ、コチなどを捕まえたようです。一方、口径3~5㎝の釣鐘形をした小型壺はイイダコを捕るための壺です。壺を海底まで沈めておきタコがその中に潜り込んだところを捕らえました。車持千年が「・・・白波の い咲き廻れる 住吉の浜」(白波の 花が咲きめぐる 住吉の浜)とうたった大阪湾。使いこまれた種々の漁具から、そこで暮らした人々の営みを垣間見ることができます。
海獣葡萄鏡
奈良時代(8世紀中葉)大坂城跡下層(大阪市中央区)
大阪府文化財センター蔵

難波宮北方で見つかった火葬墓に副葬されていました。龍の形をした鈕を持ち、内側に4体の獣と2羽の孔雀を配置しています。万葉歌には形見として贈られた鏡には想う人の姿が面影として現れると詠ったものがあり、万葉人にとって鏡は姿を見る道具だけではなく、遠く離れてしまった人に会うための呪具でもあったことがうかがえます。


難波宮造営時の整地層(7世紀中葉)直下の地層から出土した、最古の万葉仮名文木簡であり、かつ最古の歌木簡です。歌の出だし部分にあたり「皮留久佐乃皮斯米之刀斯」(はるくさのはじめの(し)とし)と読むことができます。隷書の特徴をとどめた楷書であり、中国南北朝時代(4世紀後葉~6世紀後葉)の書体と似ていることが指摘されています。
『万葉集』にこの歌のはじまりを持つ歌は見られませんが、「春草」の語が登場する歌は5首あり、勢い盛んな様子を示す一方、移ろいやすさを喩える言葉としても用いられています。