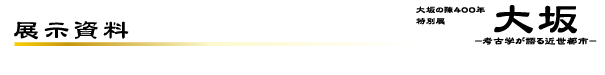
方形桐文金箔瓦(ほうけいきりもんきんぱくがわら)
16世紀 大坂城跡出土 大阪歴史博物館蔵

縦18cm、横19cm
三葉葵文鬼瓦(みつばあおいもんおにがわら)
17世紀 大坂城跡出土 大阪文化財研究所保管

高さ約82cm
大坂城本丸内にある御金蔵の近くで発掘された鬼瓦で、文様は徳川家の家紋である三葉葵文である。17世紀代に焼かれたものと考えられる。出土位置や製作年代からみて、大坂の陣後に徳川幕府によって再建され、寛文5年(1665)に落雷で焼失した徳川期大坂城の天守に葺(ふ)かれていた可能性がある。
黒織部茶碗
17世紀 大坂城跡出土 大阪文化財研究所保管

器高7.2cm、口径14.1cm、高台径5.5cm
口縁を楕円にゆがめ、胴部にヘラ目を入れる沓(くつ)形碗である。2方向に窓を残して鉄釉を塗り、窓の中には鉄絵で格子文と樹木文を描き、全体に長石釉をかける。織部(おりべ)焼は美濃地方の陶器で、豊臣後期(17世紀前葉)を中心とした限られた時期に焼かれ、茶の湯の器として珍重された。それまでのモノクロームな日本陶器とは異なり、絵画的にも造型的にも大胆な意匠は志野(しの)焼とともに時代の自由な空気を感じさせる。
化粧道具
18~19世紀 中之島蔵屋敷跡出土 大阪文化財研究所保管

近世大坂は装うことが庶民にまで浸透し、化粧や結髪が普及した。油壺は髪油の容器で、女性らしい華やかで繊細な装飾が施され、鬢水(びんみず)入れは楕円形で素朴な型紙摺り文様が特徴である。紅皿は内面に濃い紅液を塗って売られた。丹波焼の片口壺はお歯黒液を作るための鉄漿壺(おはぐろつぼ)として使われた。
神咒寺潅頂堂(かんのうじかんじょうどう)瓦笵(がはん)
江戸時代後半 瓦屋町遺跡出土 大阪文化財研究所保管

直径18.2cm
軒丸瓦の製造時に用いられた瓦製の瓦笵(瓦づくりの「型」)で、「神咒寺潅頂堂」の文字が裏返しに刻まれている。出土地の瓦屋町遺跡には、江戸幕府の御用瓦師を勤めた寺島家の工房があったことが知られているが、本資料はこの地で瓦生産が行われていたことを裏付ける。兵庫県西宮市の甲山大師・神呪寺に同じ文様の瓦が保管されている。
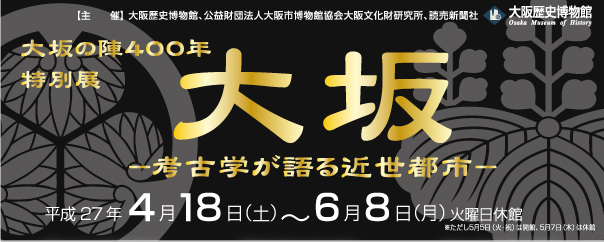

豊臣秀吉の築いた大坂城では、表面に金箔を押した瓦が多用されたことが知られている。本資料は、豊臣家を象徴する「五七の桐」文の瓦で、現在の大阪城公園の南東で出土した。豊臣期大坂城を代表する資料である。