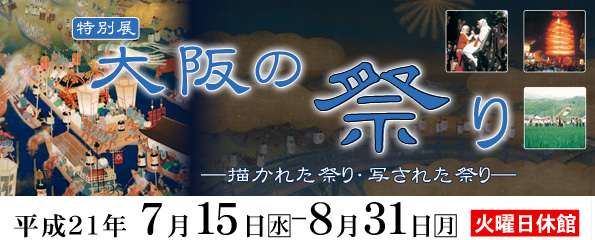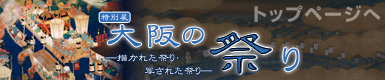雨乞祭礼図絵馬
江戸時代
岸和田市 夜疑神社蔵
1面 (岸和田市指定文化財)
雨乞祭りを描いた絵馬。画面中央下に、神社入口の淵で僧が祈祷を行い、その周囲を村人たちが太鼓や半鐘を鳴らして雨乞い歌を歌いながら巡るような様が描かれている。文政9年(1826)の干ばつの際に行われた雨乞で村が救われ、その様子を描いて奉納した絵馬が年月とともに傷んだため、慶応4年(1868)に岸和田藩の絵師、津田雲渓に依頼して描きなおさせたものである。

平野郷牛頭天王祭礼図
江戸時代
大阪市平野区 杭全神社蔵
2巻
牛頭天王すなわち杭全神社(大阪市平野区)の夏祭りの渡御列を描いたと考えられる二巻からなる絵巻。上巻には先頭の猿田彦、布団太鼓から稚児や神馬などを、下巻にはにぎやかな神輿を中心に付き従う役人などの姿を描く。奥書によれば、嘉永6年(1853)冬に往古の祭礼の列書をもとに画工に描かせたとあり、現状の祭りとは相違点も多く、江戸時代末において古い時代の祭礼の姿を復元する試みであったことがわかる。

御迎人形 与勘平
大正時代
大阪市北区 大阪天満宮蔵
1躯 (大阪府指定有形民俗文化財)
御迎人形は、江戸時代から近代に至るまで、大川下流の御旅所周辺の町々が、天神祭の船渡御を迎えるために出した船に乗せられた人形。17点の残存が確認され、内14躯が大阪府指定有形民俗文化財となっている。衣装などが赤を基調としており、疫病除けの願いが込められていると考えられている。天神祭を描いた絵画作品のモチーフにもなっている。与勘平は、文楽人形にもあるように芝居の役柄のひとつで、「うなずき」のからくりもそなわっている。
![]()